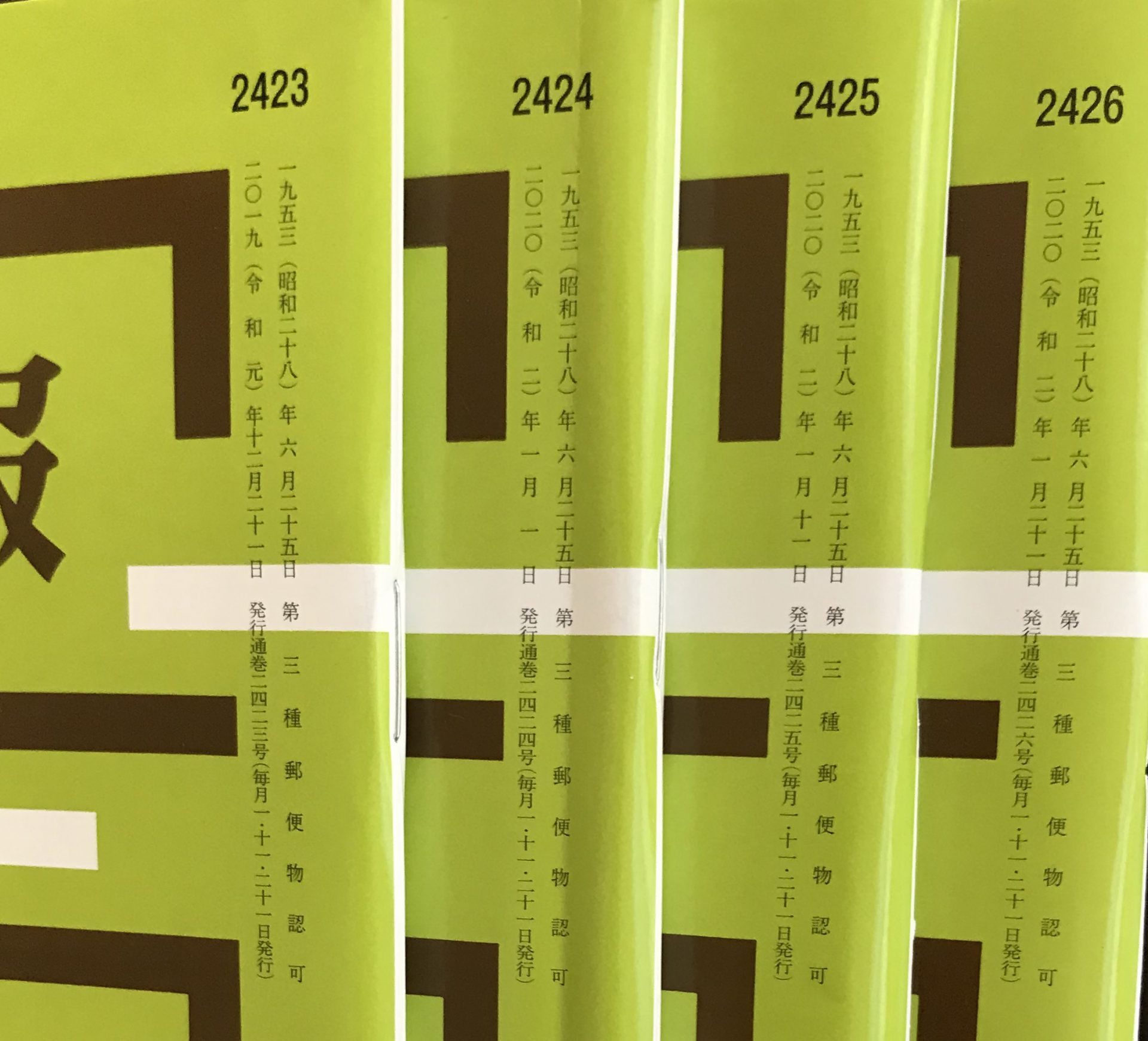月1回の判例研究会の第126回は、2023年2月27日開催され、判例時報2529~2533号から4判例が報告された。
A罪とB罪が科刑上一罪の関係にある場合においては、刑法54条により「最も重い罪」により処断されるところ、A罪もB罪も懲役刑と罰金刑を選択でき、かつ、懲役刑の長期はA罪>B罪であり、罰金刑の多額はA罪<B罪であるときに、A罪とB罪はどちらが「重い罪」なのか、罰金刑の多額はB罪によることができるのかが判断された最一判令和2年10月1日については、日頃意識しない条文を再確認する機会を持つこととなった。
負担付相続させる遺言も、負担付遺贈と同様に、相続財産の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負うとされた大阪地判令和3年9月29日については、負担のバリエーションとして個人不動産の譲渡を遺言書に記載するとどうなるか等が議論された。
離婚慰謝料は、離婚の成立時に遅滞に陥ると判断された最二判令和4年1月28日については、浪費や風俗通いが離婚慰謝料にどの程度寄与するか、不貞事例の離婚慰謝料の相場観などが議論された。
財産評価基本通達に基づく建物の相続税評価額が、時価より大幅に低いことや、借金は相続税の課税価格に含まれる(控除される)ことを利用して、相続税対策として、借金してマンションを購入し、これにより課税価格の合計額を6億円から3000万円弱に下落させ、その3年後に死亡した場合において、国が、相続人に対し、特別に、マンションについて財産評価基本通達によらず鑑定による時価評価をして課税価格を引き上げたことの有効性が争われた最二判令和4年1月28日については、いかなる事情があると国は財産評価基本通達を超える課税に踏み切るか、弁護士が相続税対策のアドバイスにどの程度踏み込むか等が議論された。