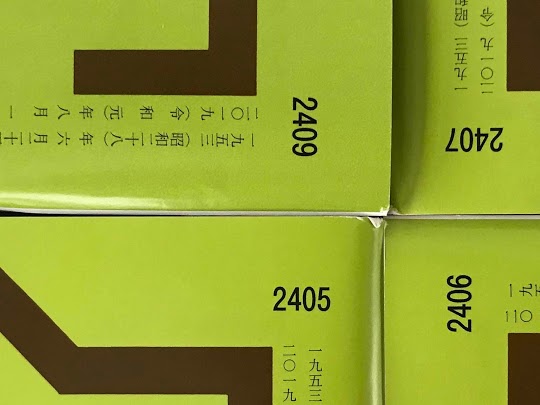月1回の判例研究会の第156回は、2025年8月21日開催され、家庭の法と裁判48~51号から4判例が報告された。
遺言書の存在を知らず唯一の相続人として遺産の不動産を占有していた者は、相続発生から14年後に遺言書の存在が明らかとなり、受贈者の相続回復請求権が発生したとしても、取得時効により抗弁できるとした事例(東京高判令和4年7月28日)、面会交流の根拠条文として主位的に民法752条「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」を主張したが却下され、予備的な民法766条類推主張が認容された事例(東京高判令和4年3月17日)、婚姻費用分担調停の申し立ての2か月前に、生活費を振り込みます、5万円とさせてくださいという夫側の申し込みと、5万円で承諾しました、ありがとうございます、というメッセージの交換があったが、このメッセージは婚姻費用の合意が成立するとした原審を覆し、正式合意成立まで暫定的に支払われる額の提案と承諾にとどまるとして支払額を増額した事例(東京高決令和5年6月21日)、非嫡出子の相続分を半分とする民法の規定は、最高裁が平成13年7月以後は違憲無効と判示したが、平成13年2月死亡の場合も違憲無効と判断した下級審事例(那覇家審令和5年2月28日)が紹介され、議論した。
第156回判例研究会