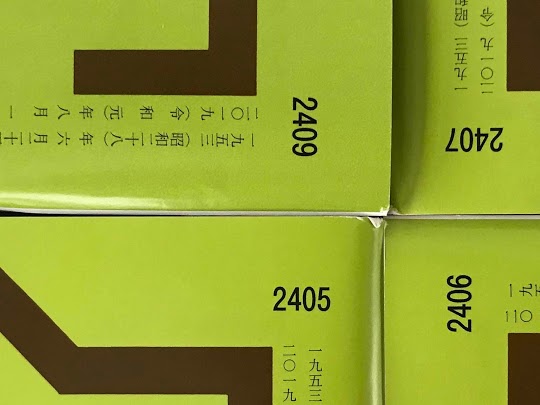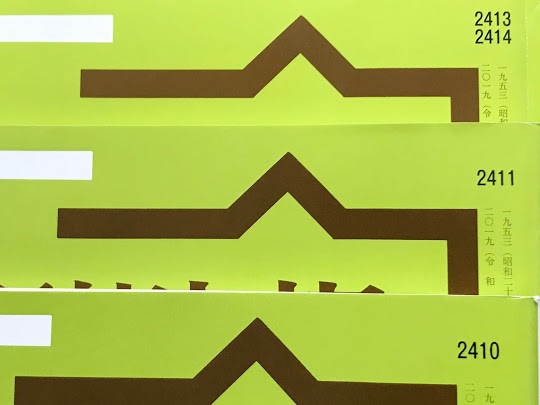月1回の判例研究会の第159回は、2025年11月25日開催され、判例時報2628~2631号から4判例が報告された。
生活保護受給中に得た給与は、生活保護費と合わせて最低限の生活を営むのに必要なものであり、実質的に生活保護費に相当するものであるから、特段の事情のない限り、民事執行法153条1項(差押禁止債権の範囲の変更)によりすべて取り消されるべきと判示した事案(大阪地決令和6年8月23日)が紹介され、債権執行全般や法定養育費等まで議論した。
マンションの59条競売訴訟の確定判決を得たとしても、競売開始決定前に被告が死亡した場合には、共同生活上の障害が解決したと考えられるので、もはや競売を申し立てることはできず、相続発生後になお共同生活上の障害が残存しているならば改めて相続人に対して59条競売訴訟をやり直す必要があるとした事案(大阪地決令和6年9月5日)が紹介され、マンション管理に係る盲点が注意喚起された。
名誉棄損のツイートがされたことを証する画像をもとに、ツイート対象者が発信者に対し損害賠償請求訴訟を提起したところ、当該画像が捏造であるとして発信者がツイート対象者及び訴訟代理人に対し反訴を提起したが、裁判所は当該画像は捏造であるが容易には見抜けないとして双方請求棄却とした事案(大阪地判令和6年8月30日)が紹介され、デジタル証拠の真実性を確認する方法を検討する等した。
依頼者本人が催告なく解除通知を送り、それを改めることなく訴訟代理人が明渡訴訟を提起し、敗訴した事案(東京地判令和6年11月28日)が紹介され、このような事案で弁護士がなすべき対応や、建物明渡請求のノウハウについて議論した。