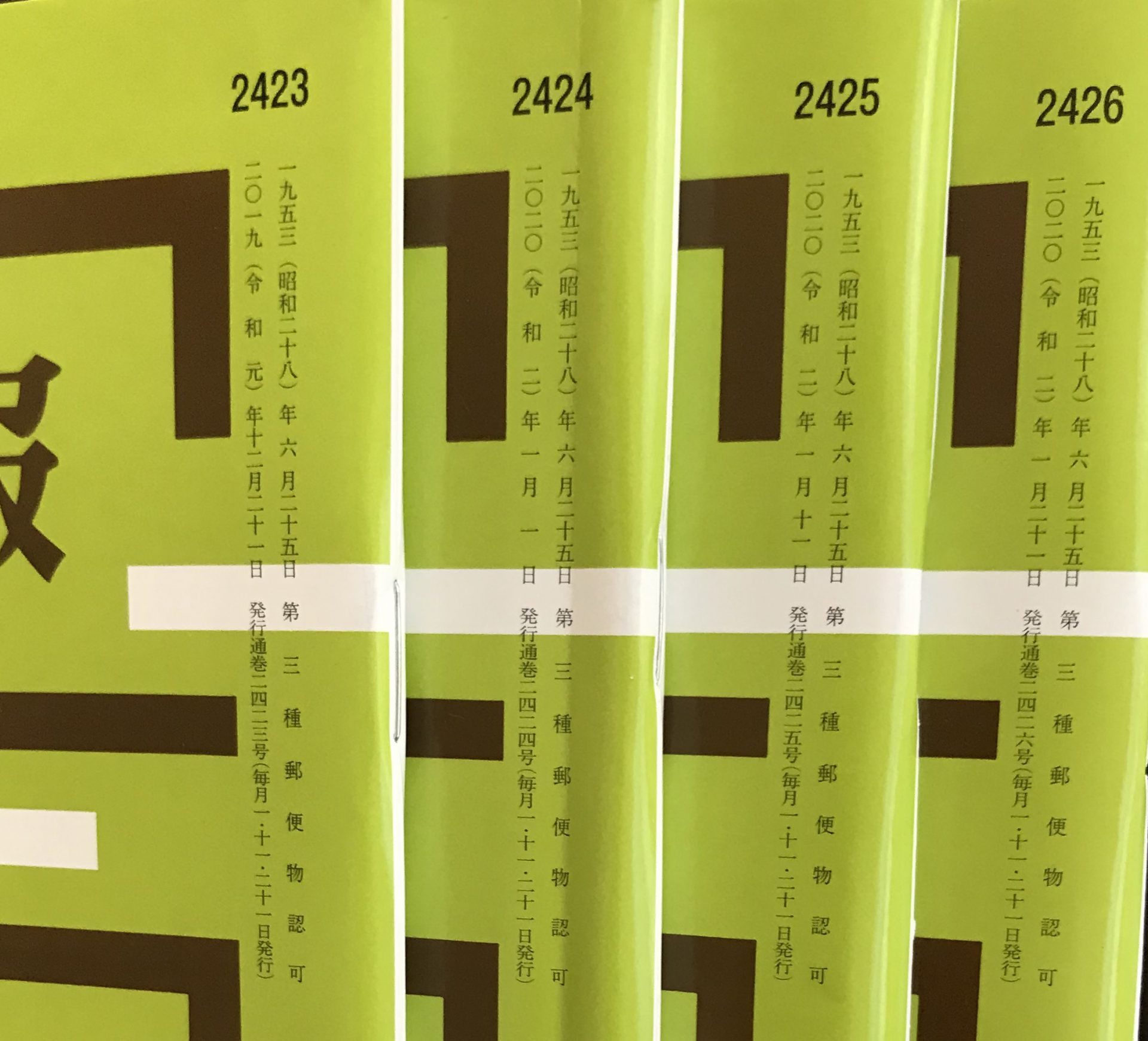月1回の判例研究会の第154回は、2025年6月27日開催され、家庭の法と裁判53~56号から4判例が報告された。
最大決令和5年10月25日と同様に、性別変更審判を認める要件の一つである「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」の規定を違憲無効として「申立人の性別の取扱いを女から男に変更する」と決定した事例(静岡家浜松支決令和5年10月11日)は、対立当事者がなく認容の場合に上訴の仕組みがないことを確認した。
祖父母が未成年者の孫を養子とした場合、非親権者である実親は第一次的な扶養義務者ではなくなるため養育費の負担を免れるとした事例(東京高決令和5年6月13日)は、相続税対策のための養子縁組を相談された場合に、頭に入れておかなければならない事例であると議論した。
財産分与対象財産中にオーバーローン不動産がある場合の財産分与に関する事例(東京高判令和6年8月21日)について議論した結果、その不動産と被担保債務については除外して、他の財産のみを分割すると考える非通算説ではなく、不動産の価値と被担保債務を通算して考える通算説が、実務上多いことを確認した。
被相続人の兄が唯一の相続人で、兄が承認も放棄もしないまま亡くなり、兄の妻と兄の子が兄を相続したが、誰も承認も放棄もしないまま今度は兄の子がなくなり、兄の子の妻子が兄の子を相続した後、兄の子の妻子がようやく、兄の子が承継した被相続人の相続分について相続放棄をしたという事例(東京高決令和6年7月18日)を通じて、再転相続の場合の相続分の移動について再学習した。
投稿者: nozomilawfirm
第153回判例研究会
月1回の判例研究会の第153回は、2025年5月30日開催され、判例時報2615~2618号から4判例が報告された。
マンションの敷地の一部が崩落して通行人が巻き込まれた死亡事故について、マンション管理組合が土地工作物責任を負うと共に、マンションの管理会社及びその従業員が条理に基づき不法行為責任を負うとされた事例(横浜地判令和5年12月15日)、インターネット上に名誉感情を害する投稿をした者が、被害者に対し、慰謝料、発信者情報開示の弁護士費用、訴訟に係る弁護士費用の支払義務を負うが、刑事告訴の弁護士費用は支払義務を負わないとされた事例(名古屋地判令和5年3月30日)、放課後デイサービスを利用していた1種知的障害A判定の7歳児が人知れず建物の外に出て、ため池で溺死したことにつき、施設の過失責任を認めたうえで、逸失利益の基礎収入を全労働者の平均賃金の5割とした事例(山口地判令和5年12月20日)、18歳による現金5000円の強盗事件について逆走せず3年の少年院送致とした事例(東京家決令和6年5月16日)が紹介され、議論した。
第152回判例研究会
月1回の判例研究会の第152回は、2025年4月23日開催され、共同親権関連の法改正についてeラーニングを受講した。制度変更は多岐にわたり、親権者を定めない協議離婚、離婚後共同親権、親権者変更の要件改正、親権の共同行使が必要な事項を共同で決められないときの家庭裁判所の審判、監護の分掌、子の監護費用の先取特権、法定養育費、財産開示手続等における自動的な給与債権情報取得や債権差押命令の申立て、婚姻費用・養育費審判における収入資産情報開示命令(制裁は10万円以下の過料)、父母以外の親族と子の面会交流、親子交流の試行的実施、養子縁組・離縁と親権者変更、財産分与の除斥期間伸長、夫婦間契約取消権や精神病の離婚原因の削除が解説された。共同親権の意見が夫婦で対立する場合に、裁判所が共同親権と定めるようになるかどうかは実務の運用を注視する必要があること、共同親権の場合における学校や病院の適切な親権者対応の在り方、先取特権に基づく不意打ち的な債権差押への対抗手段などを議論した。
第150~151回判例研究会
月1回の判例研究会の第150回は、2025年2月25日開催され、判例時報2607~2610号から4判例が報告された。遺言により相続分がないものとされた相続人は遺留分侵害額を請求しても特別寄与料を負担しないとされた事例(最一小決令和5年10月26日)、特殊詐欺の受け子をした少年の詐欺の故意を認めた判断に重大な事実の誤認があるとして取り消された事例(東京高決令和5年9月15日)、弁護士の依頼者に対する報告義務の損害賠償責任が認められた事例(東京地判令和5年5月10日)、父が借入金をもとに収益物件を建築し、子に対し借入金を免責的債務引受することを条件に収益物件を贈与し、子が収益物件の収益をもって借入金を完済した後、父が死亡した場合における、子の特別受益の価額が争われた事例(東京高決令和5年12月7日、原審は単純贈与として相続開始時の収益物件の価額×100%であるとしたが、抗告審は負担付贈与であるとして相続開始時の収益物件の価額×38%であるとした。※(贈与時の収益物件の価額-贈与時の残債務の額)/贈与時の収益物件の価額=38%)が紹介され、議論した。
第151回は、2025年3月25日開催され、判例時報2611~2614号から4判例が報告された。いじめ防止対策推進法の定義する「いじめ」は広範な行為が該当するため、同法の「いじめ」に該当するからといって当然に不法行為に当たらないとして、個々の行為の違法性を吟味した事例(東京地判令和5年10月30日)、民事事件において、職場の休憩室の秘密録音が信義則に反するとして証拠排除されたが、対面で会話した相手の秘密録音は証拠採用された事例(大阪地判令和5年12月7日)、弁護士が控訴審において依頼者の意向を確認しないまま和解の意向がない旨の記載のある照会兼回答書を提出したことが委任契約上の善管注意義務違反に当たるとした事例(大阪高判令和5年5月25日)、判決により養育費支払義務を負う父は、親権者母の虐待により子が一時保護されたときは、養育費減額審判を申し立てると申立日以降の養育費支払義務が取り消されるとされた事例(東京高決令和4年12月15日)が紹介された。
第147~149回判例研究会
月1回の判例研究会の第147回は、2024年11月18日開催され、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、フリーランス法)に関するeラーニングを受講した。
第148回は、2024年12月16日開催され、判例時報2599~2602号から4判例が報告された。抵当権の物上代位と相殺合意の優劣に関する事例(最判令和5年11月27日)、交通事故の被害者が加害者に対して有する損害賠償請求権の仮差押の効力が自賠責保険被害者請求権にも及ぶとされた事例(東京高判令和4年4月7日)、弁護士の依頼者に対する説明義務等の違反が争われた事例(東京地判令和5年1月13日)、ファクタリング業者の預金口座が犯罪利用預金口座等であるとして弁護士が凍結要請をしたが結果的に誤りであった件について不法行為責任が無いとされた事例(東京地判令和5年1月18日)が紹介され、議論した。
第149回は、2025年1月27日開催され、判例時報2603~2606号から4判例が報告された。犯罪被害者給付金の支給対象者の一つ「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーを含むとした事例(最判令和6年3月26日)、捜索差押手続中の不備により、発見された覚醒剤が犯人の所持品であると断定できなくなり、無罪とせざるを得なくなった事例(大阪地判令和5年10月13日)、仮想通貨取引による所得を婚姻費用算定における所得に含めるかどうかが議論された事例(福岡高決令和5年2月6日)、人身事故発生直後に飲酒運転発覚防止のため車両から50m離れたコンビニに行ってブレスケアを購入・服用したことで1分間を空費したことについて救護義務違反が認められなかった事例(東京高判令和5年9月28日)が紹介された(なお、2025年2月7日、最高裁にて逆転有罪となったことが報道で確認された。)。
その他、過去に取り扱ったいわゆるプレサンス事件について、報道に基づき、その後の進展状況について報告がなされた。