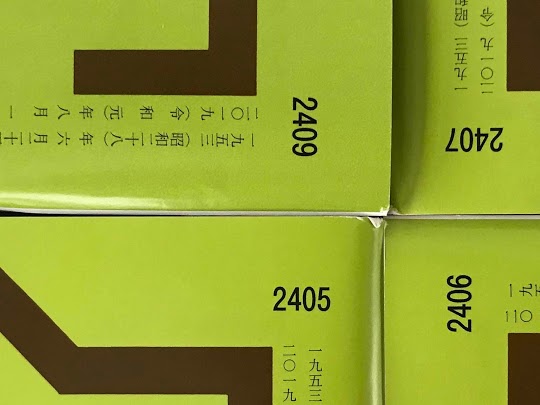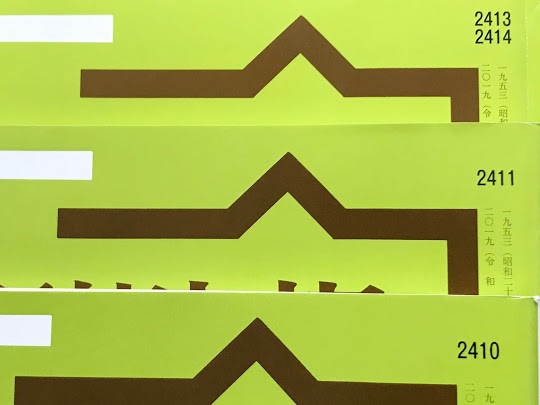月1回の判例研究会の第145回は、2024年9月24日開催され、判例時報2590~2593号から4判例が報告された。
マンション共用部分の保存の瑕疵により損害を被った区分所有者が、工作物責任に基づき他の区分所有者1名と管理組合に損害賠償請求をした事例(東京地判令和4年12月27日)が紹介された。
他の区分所有者1名に対する請求については、共用部分は区分所有者全員が占有しているので、工作物責任は区分所有者全員の不真正連帯債務となり、区分所有者各自が全額の賠償責任を負う(支払後に区分所有者間で持分に応じて求償する)のが原則である。ただし、本件では被害者が、賠償責任を負う区分所有者の一人でもあるから、他の区分所有者に対する請求は不真正連帯債務者間の求償権行使に類似するとして、持分の限度に減縮して請求が認容された。共用部分の管理は管理組合任せにすることが多いが、管理に落ち度があると区分所有者各自が巨額の責任を負いかねない。施設賠償責任への加入が重要である。
管理組合に対する請求については、管理規約の解釈により、区分所有者全員が負担する損害賠償債務の履行権限が付与されているとして、請求が認容された。しかしながら、東京高裁において判決が変更され、管理組合に対する請求は棄却されたとのことである。いかなる理由で判決が変更されたのか、追って調査しなければならない。
運動・言語に発達遅滞がみられたため1歳児クラスにおいて保育されていた3歳2か月の幼児に対し、保育士が、ホットドッグをちぎって食べさせたところ誤嚥し重大な後遺症が生じた事例(東京地判令和4年10月26日)では、パンを約5cm×2.3cm、ウインナーを直径約1.8cm×厚さ約0.7cmに与えたことに過失はなく、事故後の措置にも問題はないとして請求が棄却された。
しかしながら、勉強会終了後の報道によると、東京高判令和6年9月26日にて逆転勝訴となったようである。原典が不明であるが、「ホットドッグは厚さ5センチ、直径1.8センチ程度で、小さくちぎって与えたという市側の主張を否定した」とあるので、ウインナーの厚さの事実認定が変化し、これが厚労省ガイドラインに沿った提供方法でないとされたようである。
ガイドラインによると、ウインナーは、使用を避ける食材(プチトマト、餅、イカなど)ではなく、調理や切り方を工夫する食材に分類されており、縦半分に切って使用するとされている。家庭でも気を付けたいところである。
そのほか、大学教員任期法により無期転換ルールが緩和される「多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職」の範囲について原審と異なる判断がなされた事例(大阪高判令和5年1月18日)、当事者間の合意に基づいて養育費の支払を求める場合には、民事訴訟手続によるべきとして、原審を取り消して養育費審判の申立てが却下された事例(東京高決令和5年5月25日)が紹介された。
本日の取扱事例は、全件について高裁での逆転事例であった。第一審で不本意な判決となっても、簡単に諦めないことが重要である。