当事務所にご依頼いただいたお客様の解決事例を、ご紹介いたします。
民事事件
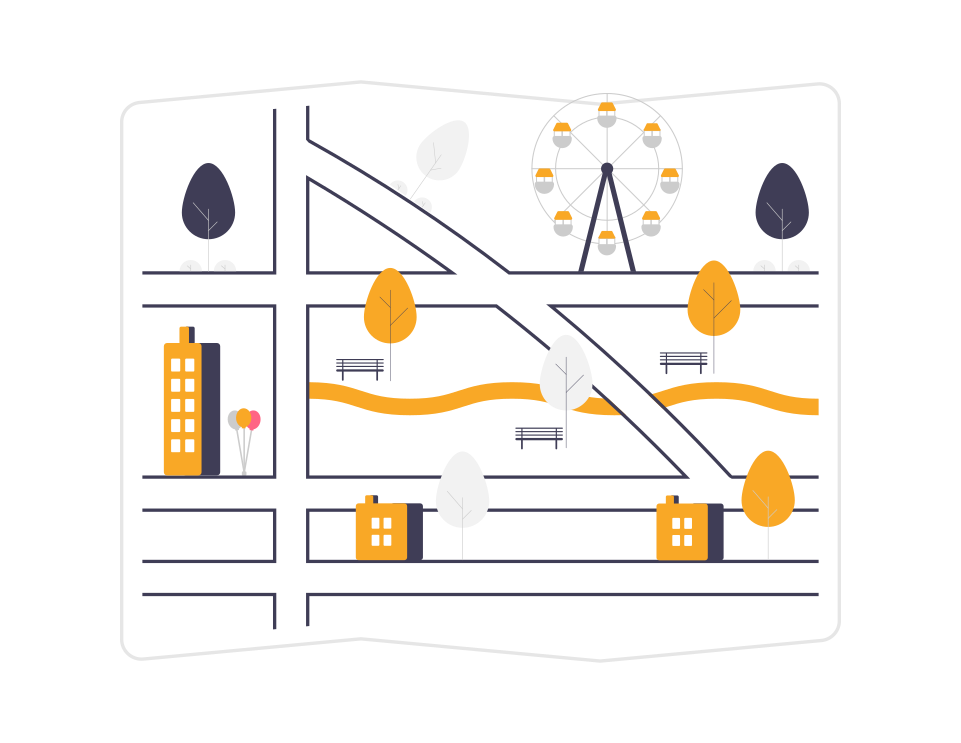
不動産登記
事案の概要
所有土地に約40年前の贈与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記が付いていました。
これは、土地の元所有者が財産を散逸してしまうことを心配して、元所有者の親族3名が持分3分の1ずつ贈与予約の仮登記をしたものでした。
その後、この土地を相談者が遺贈を受けて取得し、仮登記の権利者3名のうち2名の相続人に抹消をしてもらうことが出来ましたが、1名の相続人に抹消に応じてもらえなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決
当事務所で依頼を受け、仮登記の抹消手続請求訴訟を提起しました。真実贈与をする意思があったのではなく、財産の散逸防止のために仮登記をしたに過ぎないので、贈与予約は通謀虚偽表示(※)で無効であることを主張しました。
これに対し、被告は、元所有者に対して貸金があり、その担保として贈与予約の仮登記を設定したとの主張でした。
裁判官から、貸金の担保ということだと、親族である権利者3名で贈与予約している説明がつかないとの見解が示され、当方の主張が認められました。
訴訟上の和解においても、被告は、金銭の支払いを要求してきましたが、当方は、他の2名の権利者は金銭の支払い無く抹消に応じており、被告に対してのみ金銭を支払う理由はないと主張しました。その結果、裁判所も当方の主張を認め、何らの金銭の支払い無く、被告が仮登記を抹消する内容の和解が裁判所から示され、和解が成立しました。
*通謀虚偽表示
「通謀虚偽表示」とは、相手方と通じて真意ではない意思表示を行うことをいいます。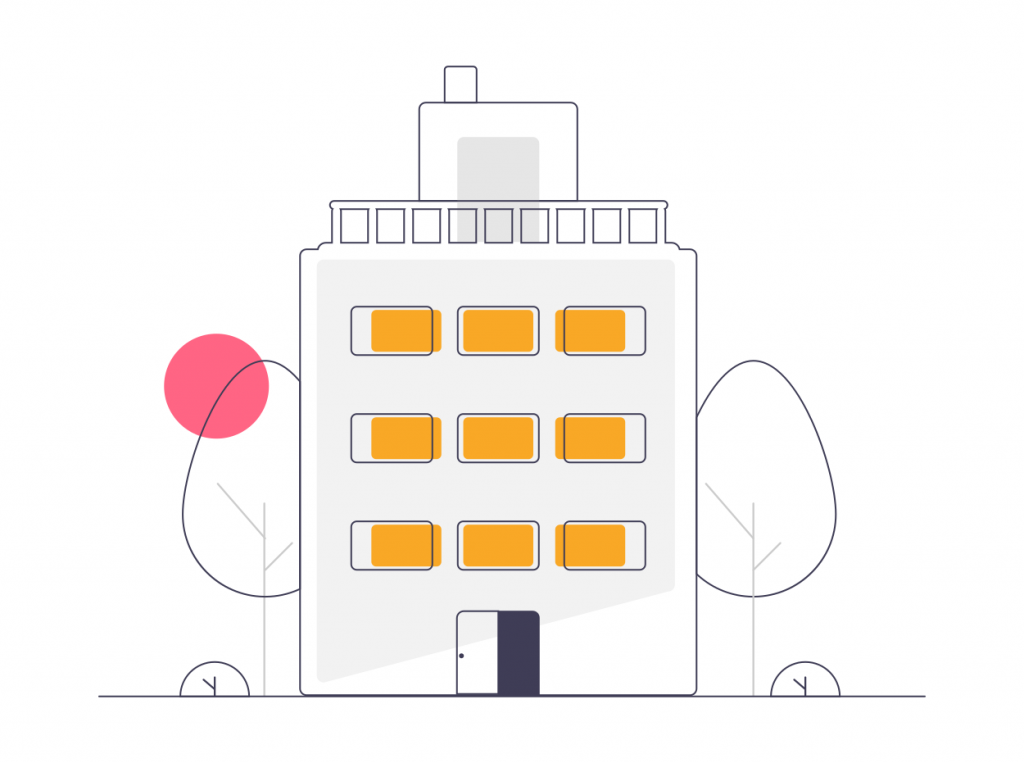
賃貸借
事案の概要
持ちビルの1室をテナントとして貸していたところ、借主が賃料を滞納したまま行方不明となったことで困り、相談にいらっしゃいました。
解決
借主本人に対する建物明渡請求訴訟と、連帯保証人である親に対する保証債務履行請求訴訟を提起しました。
借主本人は、行方不明なため、住民票上の住所の調査を行い、そこに住んでいないことが明らかとなったので、公示送達の方法により訴状を送達しました。これにより、建物明渡判決を取得し、強制執行手続を行って明渡しを実現しました。
親に対する保証債務履行請求訴訟では、最終的に親と裁判上の和解を行い、滞納賃料を回収しました。
事案の概要
借地法の適用のある借地権(※)及び借地上の建物を相続し、居住していた依頼者が、賃貸人から、短期間の賃貸借かつ高額な賃料への条件変更を迫られ、その旨の記載のある賃貸借契約書に署名・押印したが、長期的に居住し続けることを希望し、相談にいらした事例
解決
変更後の賃貸借契約の無効確認調停を申立てました。
相手方は、変更後の賃貸借契約は、従前の賃貸借契約を合意解約し、明渡しを猶予したものである旨主張しましたが、判例を検討し、相手方の主張は判例上通用しない旨反論しました。
その結果、依頼者が、賃貸借期間の定めのない借地法の適用のある借地権を有していることを確認すると共に、賃料を段階的に増額するものの、その上限は変更後の賃料の2分の1以下までとする内容で調停が成立し、解決しました。
*借地権
建物所有目的の土地賃借権であり、賃貸借期間を定めず、木造建物を所有する場合、その期間は30年とされ、その後も20年ごと更新される権利

ゴルフ会員権預託金
事案の概要
遺産の中にゴルフ場会員権と預託金債権があり、据え置き期間経過後も長らく預託金が返還されていなかった件で、預託金を回収できないか相談がありました。
解決
相続人の一人が遺産分割により預託金債権を取得した上、内容証明郵便で退会の意思表示をし、預託金数百万円の返還請求を求めました。訴訟提起前のゴルフ場運営会社からの提案額は少額であったため、訴訟提起をしました。
欠席判決で勝訴判決を得ましたが、被告からは何ら支払いがなかったため、強制執行により執行費用、遅延損害金もあわせて全額回収しました。
事案の概要
相談者は、ゴルフ場会員権と共に預託金債権も譲り受けましたが、据え置き期間経過後も長らく預託金が返還されず、年会費の請求書が届いていましたので、預託金は返してもらえないのか、とのご相談でした。
解決
内容証明郵便で退会の意思表示をした上、預託金300万円の返還請求を求めました。
訴訟提起前のゴルフ場運営会社からの提案額は少額であったため、訴訟提起をしました。
ゴルフ場運営会社からは年会費の請求がありましたが、時効援用により時効消滅させ預託金全額の勝訴判決を得ました。
それでもゴルフ場運営会社からは任意に支払われなかったため、強制執行により執行費用、遅延損害金もあわせて全額回収しました。

悪質商法
事案の概要
「求人広告を一定期間無料で掲載できる、無料期間経過後に有料で掲載を継続するかどうかは事前に意思確認する」との勧誘電話を信じて、広告掲載を依頼したところ、確認の電話がないまま、自動更新条項により有料更新され、多額の請求書が、毎日のように送られてくるようになったことから、相談にいらっしゃいました。
解決
求人広告業者に対し、支払を拒絶する旨の内容証明郵便を送付しました。
すると、求人広告業者から、金額を下げての和解を希望すること、和解しなければ裁判も辞さないことの電話を受けました。
検討の末、和解を拒絶しましたが、請求は止まり、提訴も無く、そのまま解決となりました。

交通事故
事案の概要
依頼者が右折で路外の駐車場に侵入しようとしたところ、反対側車線に停車していた相手方車が突然公道上を後退してきて、依頼者の車両に衝突した事故が発生しました。
相手方は、ハザードランプを点けていたから、後退することを予測すべきで自分に非は無いとの主張でした。相手方保険会社も自損自弁(※)の提案でした。
そこで、依頼者は当事務所にご相談にいらっしゃいました。
解決
当事務所で依頼を受け、損害賠償請求訴訟を提起しました。
当方は、相手方車両が公道上を後退してきて、同じ駐車場に入ろうとする変則的な運転は、ハザードランプを点灯したとしても予測できないと主張しました。
他方で、相手方は、訴訟においては、過失割合について当方4:相手方6を主張していました。
裁判所の和解において、裁判所は、ハザードランプの意味は複数あり、通常、このようなケースで後退することは予測できない、この駐車場に後退で入ること自体が危険と判断し、過失割合は当方2:相手方8で和解が成立しました。
*自損自弁
「自損自弁」とは、自車の修理費用を自分で負担するという合意をいいます。
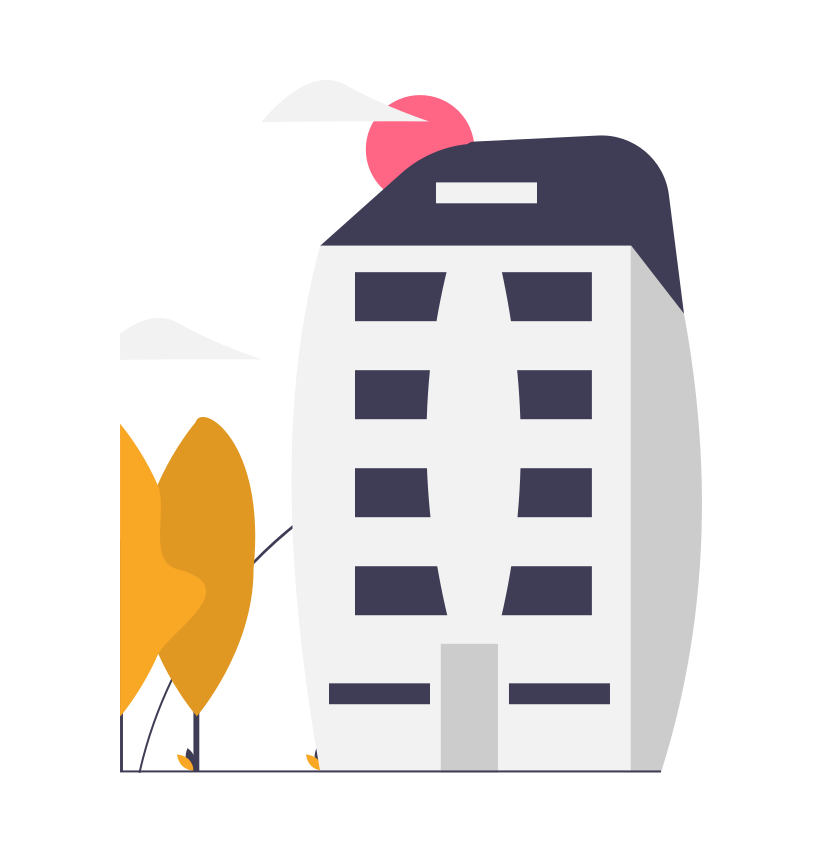
マンション管理組合
事案の概要
既にマンション管理組合自身が、滞納管理費の支払督促手続(※1)を行ったものの、その後も区分所有者(※2)が支払わず、困って相談にいらっしゃいました。
解決
区分所有者は当該マンションに居住しておらず、賃借人が居住しているとの情報を得ました。
そこで、賃借人の情報を収集して、賃借人が区分所有者に対して毎月支払っている賃料を差し押さえました。
これにより、賃借人が区分所有者ではなくマンション管理組合に対し、賃料を支払うようになり、支払督促で請求していた滞納管理費を全額回収しました。
*1 支払督促手続
債権者からの申立てに基づいて、簡易裁判所書記官が債務者に対して金銭等の支払いを命じる制度。代理人を立てずに債権者本人が手続きするのに利用されることが多いです。
*2 区分所有者
分譲マンションなどを法律用語で「区分所有建物」といいますが、その居室部分(専有部分)を所有している者のことを「区分所有者」といいます。
事案の概要
マンション管理組合からのご相談で、管理費の滞納が発生したが督促や電話をしても当該区分所有者(※)と連絡がつかず、困って相談にいらっしゃいました。
解決
区分所有者について調査した結果、亡くなっていたことが判明しました。
次に、相続調査を行い、相続人の氏名と所在を明らかにしました。
そして、相続人らに対して内容証明郵便で管理費等の請求をしました。
その結果、相続人の一人から連絡を受けて、比較的スムーズに管理費等を全額回収することができました。
*区分所有者
分譲マンションなどを法律用語で「区分所有建物」といいますが、その居室部分(専有部分)を所有している者のことを「区分所有者」といいます。
家事事件

財産管理
事案の概要
失踪していたご兄弟が発見され、市に保護されました。ご兄弟は、昏迷状態が続いていましたが、徐々に記憶が戻り、意思疎通が一応可能な状態となりました。ご兄弟は、マンションのローンの支払いが出来ておらず、債権者から競売申立がなされ、すでに所有マンションは、担保不動産競売により売却がなされていましたが、まだ負債が残っている状態でした。
そこで、遺産で相続した不動産を売却しようとしましたが、依頼者からこのタイミングで当事務所にご相談いただきました。
解決
ご兄弟の意思能力に疑問があったため、医師の診断書を作成し、保佐相当ということだったため、裁判所に保佐人の選任申立を行いました。申立後、病院で家庭裁判所の調査官と本人を含めて面談し、その後、保佐人の選任が認められました。
その結果、保佐人がご兄弟を代理して不動産を売却することができました。
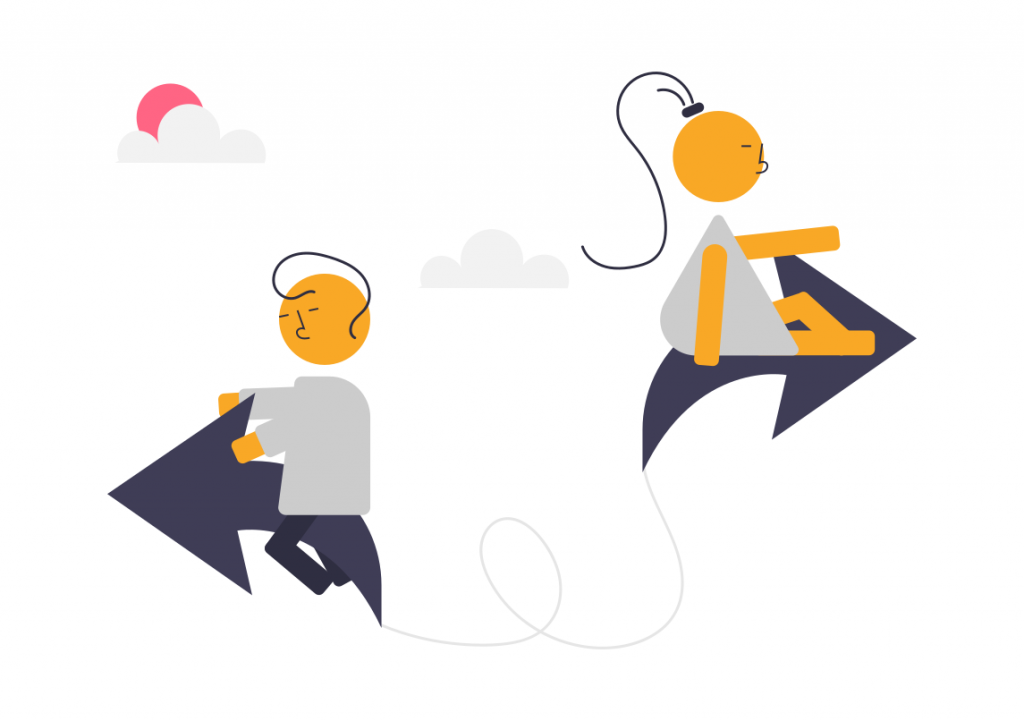
遺産分割
事案の概要
相談者が亡祖母や亡父名義の不動産に居住していたところ、亡父の死亡から相当期間経過後に、亡父の債権者から、相談者を含む共同相続人に対し、多額の相続債務の請求がなされたため、相談にいらっしゃいました。
解決
相続放棄が困難な事情があったため、相続承認を前提とした交渉による解決を模索することにしました。当事務所が代理人として債権者と連絡を取り、債権の存否の確認や、減額交渉を行いました。最終的には、不動産を換価した代金を支払いに充てるが、その後に残る債権については共同相続人全員に対する請求を断念してもらうことになりました。
共同相続人との間で遺産分割協議を成立させ、不動産を相談者の名義に変更しました。
その後、当事務所を通じて不動産業者に依頼して、換価を行いました。不動産は、相談者が居住していましたが、売買代金から引越費用の控除が認められた為、資金の持ち出しなく転居することができました。
当事務所を通じて税理士に依頼し、不動産売却に伴う税金等の諸経費を算出し、これを売却代金から控除した残金を、債権者に弁済し、解決となりました。
事案の概要
療養中の弟の日常生活や入院中の世話を無償でしてきた依頼者が、弟から口頭で頼まれて通帳や印鑑を預かり、必要な事務処理を行ってきました。
弟の死亡後、生き別れとなった子(唯一の相続人)がいることが判明し、相談にいらっしゃいました。
解決
依頼者は、全遺産を弟の子が相続することを了承していたものの、弟に依頼されて行ってきた事務処理への承諾と、無償で世話を行ってきたことに関して特別寄与料の支払い(※)を求めることを希望していました。
そこで、弟の子に対し、全遺産を開示すると共に、依頼者が行ってきた世話の内容、通帳等を預かった経緯や事務処理の内容等をまとめた陳述書を作成して送付し、理解を求めました。
その結果、依頼者は全遺産を弟の子に引き渡し、弟の子は依頼者が行ってきた事務処理を正当な行為と認め、依頼者に特別寄与料を支払う内容で合意が成立し、解決しました。
*特別寄与料の支払い
被相続人の財産の維持又は増加への寄与に応じた額の金銭の支払い

遺言・遺留分
事案の概要
入院中の患者様から、遺言書を作成したいとのご要望をいただき、病室にて相談を受けることになりました。
解決
お子様たちとは長年音信不通であり、お世話になった方々に遺産を渡したいとのことでした。
しかし、余命が限られているため、公正証書遺言を作成する暇はなく、また、自筆で遺言書を作成する体力が残されていらっしゃいませんでした。
そこで、依頼者の意向を聞き取り、病院にて危急時遺言(*)を作成しました。
その後、依頼者が亡くなった後、裁判所で遺言書の検認手続きを行い、遺言執行者として、相続人の方に遺留分をお支払いした上で、依頼者の遺言のとおり執行しました。
*危急時遺言
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者であっても、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、遺言を作成することができ、これを危急時遺言といいます。
作成してから6か月間生存すると、危急時遺言は失効します。
顧問契約
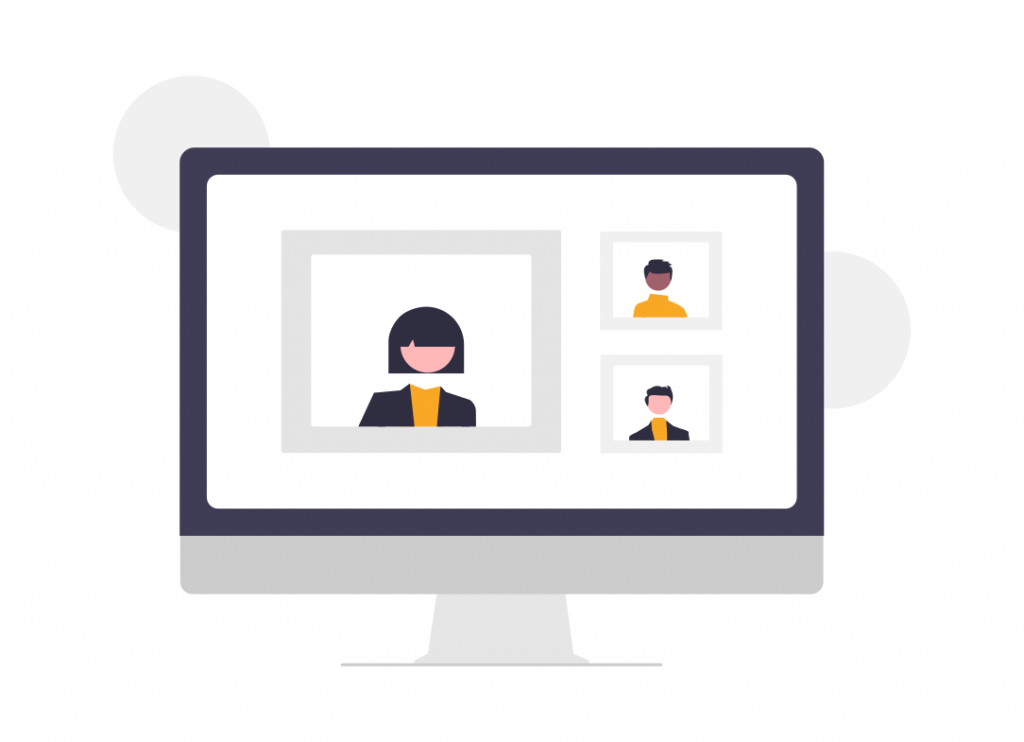
顧問契約の活用事例
事案の概要
複数の顧問弁護士を有する顧問先から、短期間で契約書チェックを対応することができるのは当事務所であろうとのことで、細かい字で70頁超の契約書原案のチェックを依頼されました。
多数当事者が関わる契約であり、厳格なスケジュールが組まれていたため、短期間で完成させる必要がありました。
解決
原案を確認したところ、全体的な書き換えが必要でした。
契約締結後の様々な不測の事態、あるいは事情変更に備えた契約条項を設ける必要があるため、契約書作成には相当量の労力が必要であり、所内で複数弁護士による態勢を迅速に整えました。
そして、できる限りの契約書作成作業を行ったうえ、顧問先の依頼であるため特別に、長期休暇中においても作業を実行し(顧問先の担当者も同休暇中に稼働していました)、スケジュール内に完成させることができました。
契約締結から数か月後に、早速、不測の事態が発生しましたが、あらかじめ準備しておいた条項により紛争には至らず、更に、違約的な手数料を徴求するなど顧問先に有利な結果に運ぶこともできました。
事案の概要
顧問先の施設内でお客様が転倒し、大怪我をされました。
施設賠償責任保険に加入していましたが、交通事故とは異なり保険会社は示談を代行しないので、顧問先担当者が窓口となってお客様に対応していました。
顧問先は、お客様への対応の一環として、即時に、事故とは無関係の費用を免除するなどしていましたが、このような免除金は、直接的には保険金の支弁対象とはならないため困っており、相談のメールを頂きました。
解決
法律上認められる損害額については保険金が全額支給される契約でしたので、保険金の事前算定を行ってもらいました。
そして、免除金については法律上認められる損害額の一部を先払いしたものと扱う前提で、示談することをご提案しました。
また、お客様への説明予定稿を事前に確認し、加除修正の意見を伝えました。
その結果、保険金の範疇で示談が成立し、顧問先の経済的負担は無くなりました。
なお、顧問先へのサービスとして承っている随時のメール相談のみで解決し、代理人選任には至りませんでしたので、顧問料以外の弁護士費用は発生しませんでした。
