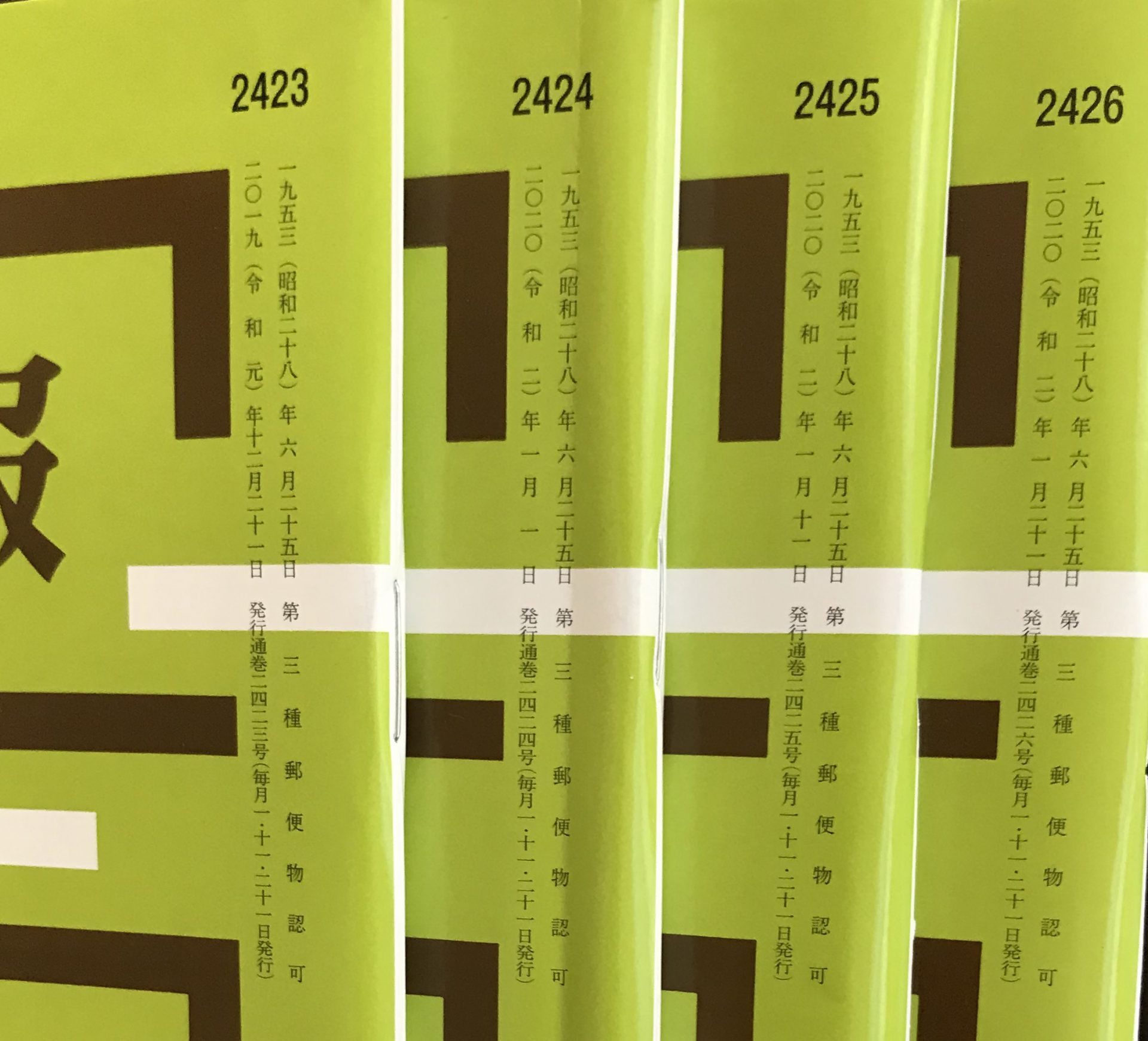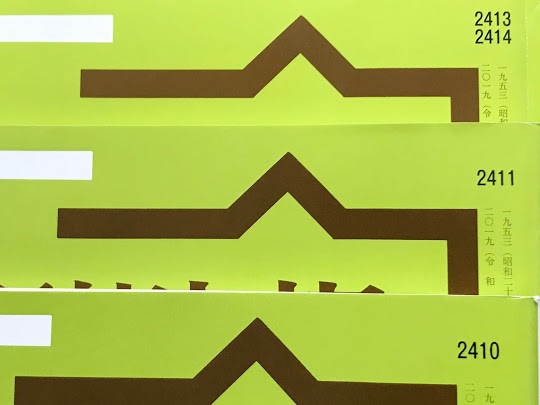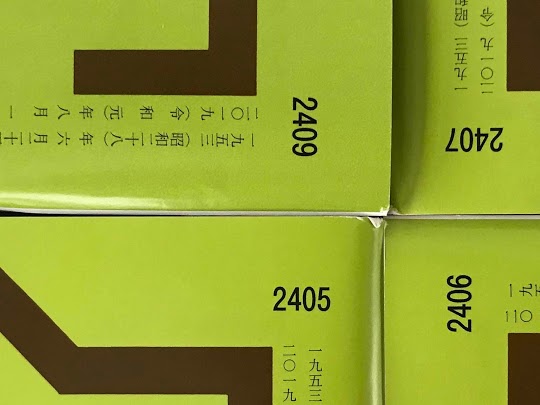月1回の判例研究会の第127回は、2023年3月29日開催され、判例時報2534~2537号から4判例が報告された。
町内会は、法人格を持たないため所有権を直接有することはできず、構成員全員に帰属し(総有)、登記が必要な場合は、理事などの個人名で登記する運用である。しかるに、町内会が共有持分権(所有権)を直接有することの確認を求める訴訟が提起された。これを審理した高等裁判所が、構成員全員に総有的に帰属することの確認を求める趣旨に出るものであるかの釈明を求めることなく、町内会は共有持分権の主体たり得ないとして棄却したのに対し、最高裁が、高等裁判所の釈明義務違反を理由に審理の差し戻しを命じた事例(最判令和4年4月12日)を取り扱った。原告・被告の立場となる我々としては、主張・反論の問題点、漏れについて逐一点検することが肝要であると考えさせられた。
祖父母が面会交流審判を申し立てることは許されないと判断された事例(最判令和3年3月29日)については、祖父母は家事事件手続法244条の家事調停を申し立てることができることが指摘されているが、制度として十分とはいえず、立法的な解決が期待される。
亡くなった被相続人が掛けていた生命保険の死亡保険金は、受取人の固有財産となり遺産に含まれないのが原則であるが、状況によっては特別受益に準じた持ち戻しの対象となるとされており、これを否定した事例(広島高判令和4年2月25日)が紹介され、いかなる場合に持ち戻しの可能性が出てくるかを皆で議論した。
その他、人身傷害保険や自賠責保険の代位に関する最判令和4年3月24日が紹介され、結論を把握しておき、交通事故実務で見落としをしないよう努めることとした。