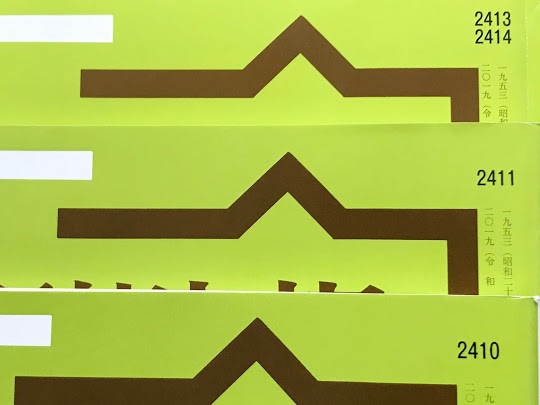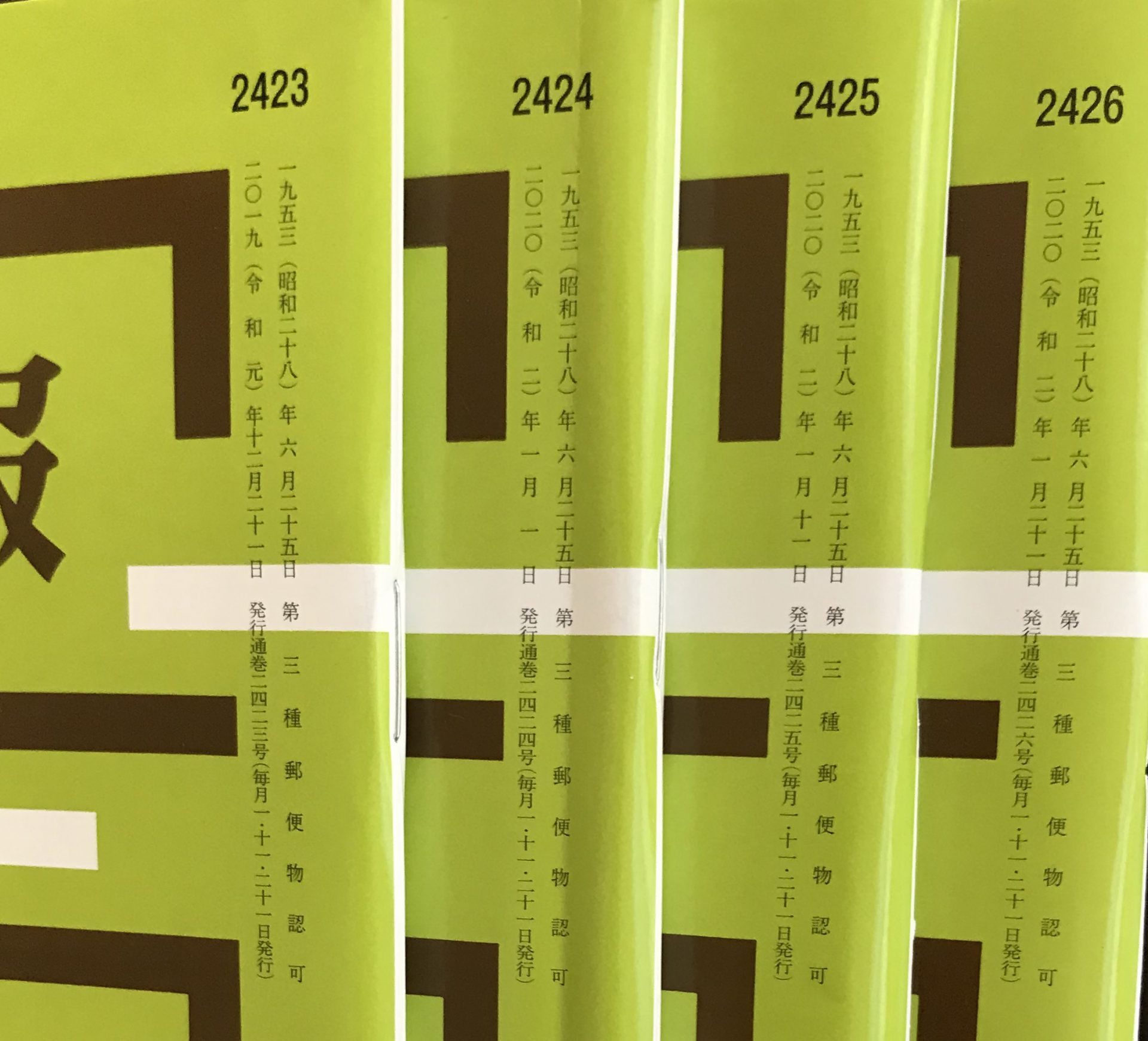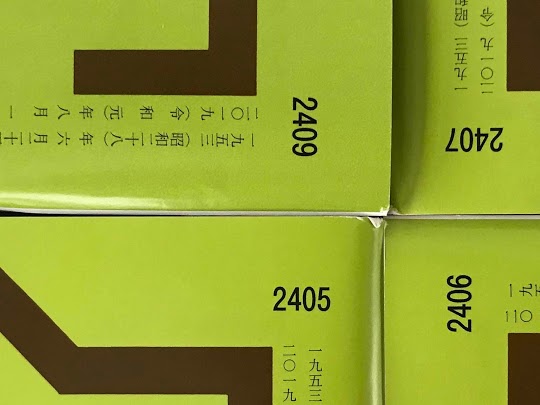月1回の判例研究会の第118回は、2022年5月30日開催され、判例時報2502~2505号から4判例が報告された。昭和34年に集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに持続感染した者が、昭和62年にHBe抗原陽性慢性肝炎を発症し、平成19年にHBe抗原陰性慢性肝炎を発症した場合の、不法行為の除斥期間の起算点について判断した最判令和3年4月26日が紹介された。継続的不法行為に関する議論と共に、参加者から、当県におけるB型肝炎訴訟の状況が報告された。その他、雇止めに関する東京地判令和2年10月1日、民法1027条(負担付遺贈に係る遺言の取消し)に関する仙台高決令和2年6月11日、なりすまし口コミの削除請求に関する大阪地判令和2年9月18日が紹介された。
第119回は、2022年6月29日開催され、判例時報2506~2509号から4判例が報告された。大規模半壊とする罹災証明書に基づき支援金が支給された後に、自治体の調査により罹災証明書が一部損壊に変更され、支給決定の取消決定が行われた事案で、授益処分の職権取消しの要件が検討された最判令和3年6月4日、懲戒解雇された労働者に対する退職金全額不支給措置が適法とされた東京高判令和3年2月24日、交通事故以外に原因が考えられない一方で、医学的な機序について必ずしも説明が十分とはいえない後遺障害に関して判断された札幌高判令和3年2月2日、破産事件の否認権行使に関する東京地判令和2年1月20日が紹介された。