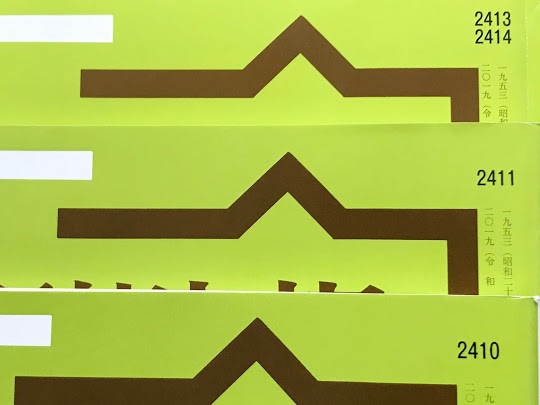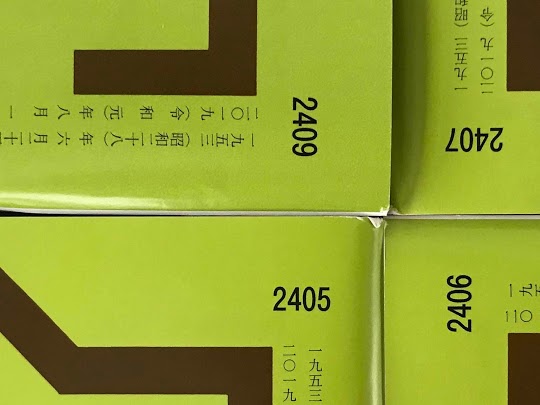月1回の判例研究会の第109回は、2021年8月30日開催され、判例時報2470~2473号から4判例が報告された。1件は、給与ファクタリングを装った出資法違反の貸金の事案(東京地判令和2年3月24日)である。これに関連して、後払い現金化についても議論となった。後払い現金化は、2021年6月16日に消費者庁から注意喚起資料が公開されている問題であり、注意を要する。
https://www.caa.go.jp/notice/entry/024625/
その他、年金の受給開始時期を遅らせた場合の婚姻費用の算定方法を明らかにした事案(東京高判令和元年12月19日)、国民健康保険税の消滅時効の中断に関する事案(最二判令和2年6月26日)、同性カップルの一人が異性と性的関係を持ったことで事実婚が破綻した場合の損害賠償請求が認められた事案(東京高判令和2年3月4日)が紹介された。
第110回は、2021年9月27日開催され、判例時報2474~2477号から4判例が報告された。1件は、ストーカー規制法における「住居等の付近において見張り」をする行為には、無断でGPS機器を取り付けて位置情報を遠隔取得する行為は含まれないとされた事案(最判令和2年7月30日)である。これに関連して、GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得を別途規制対象とする令和3年8月26日施行の改正ストーカー規制法が紹介された。その他、ハウスクリーニング事業の機材等販売・開業支援等を内容とするフランチャイズ契約が、特商法の業務提供誘引販売業(内職商法、サイドビジネス商法の規制)に該当するとされた事案(大津地判令和2年5月26日)、夫名義で妻が占有する夫婦共有財産の不動産について、裁判所は、離婚時に妻に分与しないものと判断した場合でも「財産の分与に関する処分の審判」に基づく不動産の引渡命令を出すことができると判断された事案(最判令和2年8月6日)、婚姻費用減額審判の第一審で減額が認められたが、減額が不十分であるとして抗告したところ、抗告審で逆に減額不要であると不利益変更された事案(大阪高決令和2年2月20日)が紹介された。