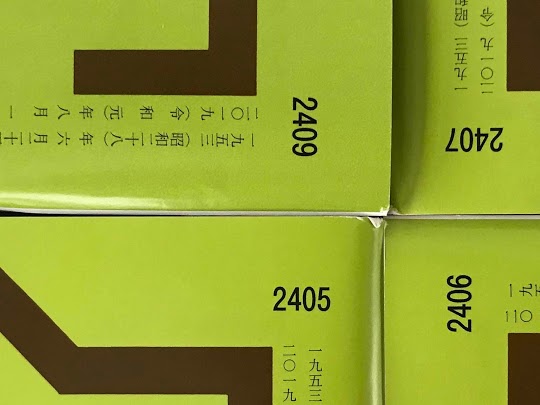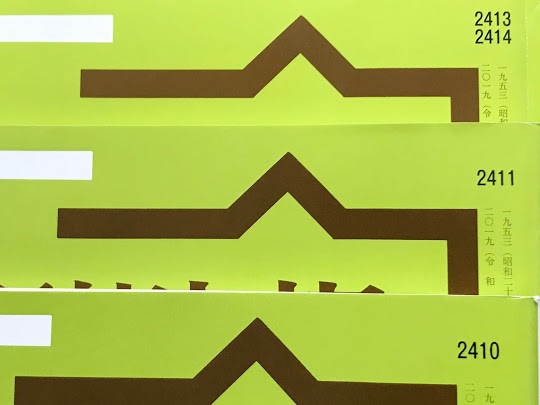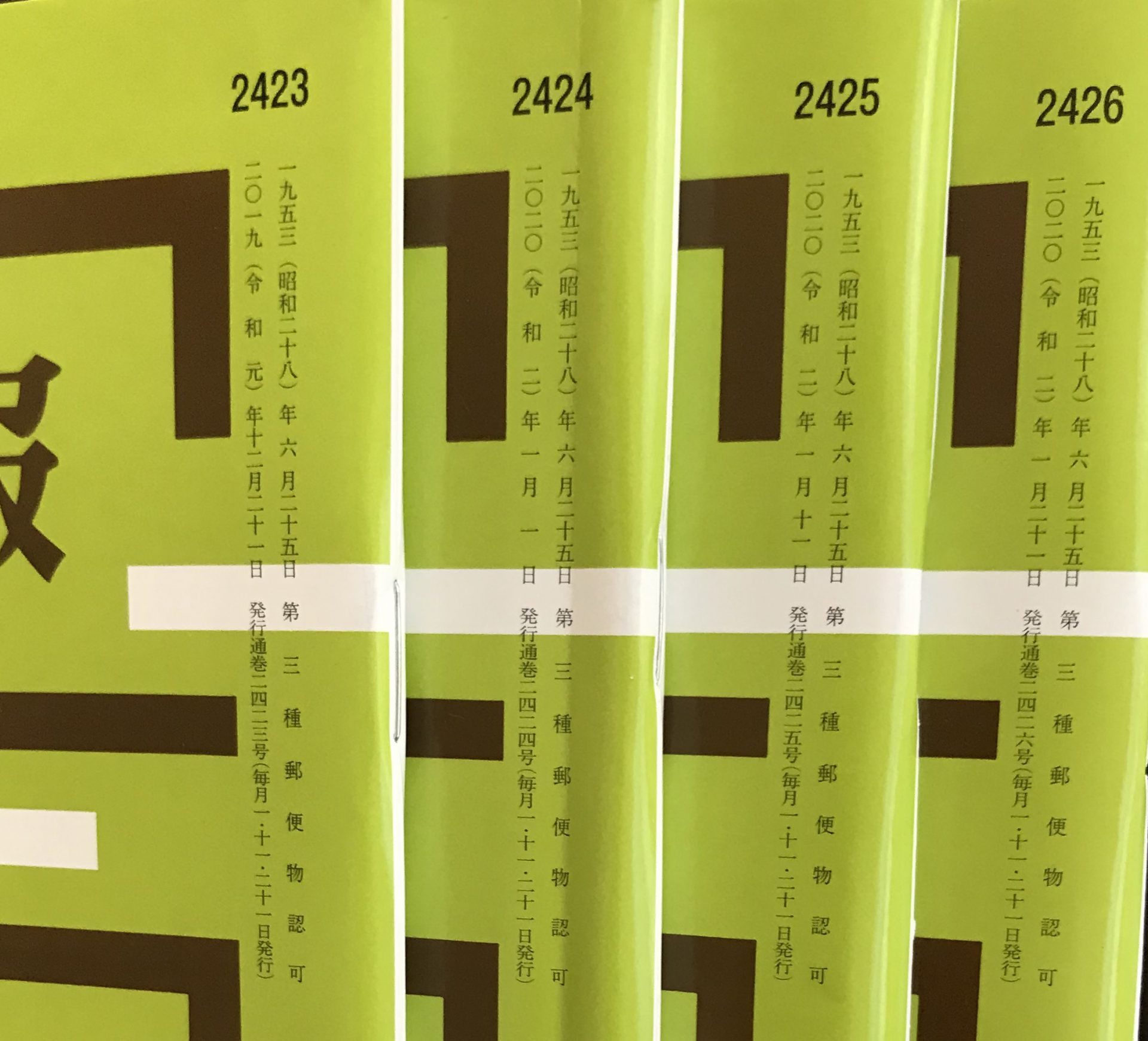月1回の判例研究会の第135回は、2023年11月22日開催され、判例時報2557~2560号から4判例が報告された。
拳銃を強取するつもりで警察官を殺したのか(強盗殺人)、警察官を殺してから拳銃を取る意思が生じたのか(殺人+窃盗)が地裁と高裁で判断の別れた事例(名古屋高判令和4年3月24日)、家賃保証会社の契約書について適格消費者団体が提訴した事例(最判令和4年12月12日)、袋地所有者が行動への通路所有者に対し、通行や工事の妨害禁止を求めて認容された事例(東京地判令和4年3月23日)、転籍出向を前提とする退職の意思表示が心裡留保により無効とされた事例(令和4年1月26日)が紹介され、議論した。
第136回は、2023年12月27日開催され、判例時報2561~2553号から2判例が報告された。
自分の名前をツイッターで検索すると、7年以上前の犯罪報道記事の紹介ツイートが検索結果として出てくるのは、犯罪事実を公表されない法的利益が、ツイートを一般の閲覧に供し続ける理由に優越するので、プライバシー侵害に当たるとして、ツイッター社に削除を命じた事例(最判令和4年6月24日)、固定残業代に関する事例(東京地判令和4年1月18日)が紹介され、議論し、忘年会となった。